先日行われた一般社団法人ALFAEさんのセミナーを拝聴して感じたこと
結局のところ、今年の米騒動に限らず、「予測された作況指数」と「品質というフィルタにかけられた精米量」との間にズレが生じていたことが主な原因だったと感じました。これは数ヶ月前にNHKの日曜討論でもコメ生産者の代表者が同じような意見をしていたことが思い出されました。個人的にはもう一歩踏み込んで考えてみたいと思います。
作況指数を平年並みと発表してしまう事のメリットとデメリット
まずメリットは、市場のパニックを防ぐことと、価格の安定化が挙げられます。また、生産者への過度なプレッシャーがなくなること などもあるかと思います。
次にデメリットですが、メリットと表裏一体。
作況指数が平年並みと発表され価格の安定が確保されることはつまり、価格が平年並みに「安定」してしまい、
初期段階で出荷するコメ農家の収入が減る可能性があるのではないかと思います。(振り返ると、農家が減っているのに作況指数が毎年のように平年並みで推移することも少し疑問が残る。。。)
それを見越して、卸市場が安く購入し、価格が高騰するのを待ってから放出する可能性を否定できません。
米を高品質のまま保管しておく巨大な倉庫をもっていない米農家も少なくありません。
さらに(国の統計がどこまで正確かにもよりますが)、精米後の品質のデータが仮に誤っていたとすると、
農家の収入に大きな影響が出るのではないでしょうか。
さらにそれを見越した卸業者やJAが利益を高める可能性があるのではないかと強く懸念するところであります。
つまりまとめると、作況指数が「平年並み」は農家にとって今後不利になる可能性が極めて高いです。
精米後の品質割合は、仮にそのデータが悪意を持って低く捏造されてしまうと、
これまた市場価格が跳ね上がり、結果農家が不利になり、卸がその利益を得るという構造が出来上がってしまいます。
結局しわ寄せが来るのは農家か
卸有利・農家不利の構造が改めて露呈した形だと思います。
価格が上がるのを見越して米を先物取引的に扱うものが得をする構造が透けて見えます。
本当にそうか?を以下chatGPT(無料版)で検証
作況指数が『平年並み』と発表されることで初期相場が抑えられ、
出荷タイミングの早い農家が低価格で売らざるを得ない一方、保管力のある卸・JAが安値で買い溜め
→高騰時に放出して利益を得る可能性――は十分に起こり得るのか?と質問してみました。
裏付けになる観察ポイントは次の通り。
- 時差(ラグ):作況・発表 → 卸相場の動き → 農家の実受取(集荷価格や買取価格)。もし卸価格(相対取引価格)が上がるのに農家の平均受取がその上昇に追いついていなければ、流通側が有利になっている可能性がある。
- 出荷先の変化:データ上、2024→2025で「JA等への出荷(集荷)減」「生産者の手元在庫増・直販増」が観察されている(流通構造の変化)。これが農家の「出し渋り」や卸の買い方の変化を示唆する。MBAならビジネス・ブレークスルー大学大学院(BBT大学院)
- 民間在庫と保管力:卸やJAは保管・流通インフラを持つため、安値期に買って保有→高値期に放出してトレード差益を取るインセンティブがある。MAFFの相対取引価格や民間在庫データでこれが示唆される年がある。農林水産省+1
- 品質情報の非対称性:作況指数は「籾量」中心で、精米後の歩留まりや品質(胴割れ・乳白粒など)を即反映しにくい。流通・検査現場に近い事業者の方が早く品質低下を察知できるため情報格差が発生しやすい。農林水産省Kubota
これらを取り扱う指標(MAFF等の公的データから取得)
- 農林水産省:作況指数(年/月)と作況発表時点。農林水産省
- MAFF:相対取引(卸)価格の月別推移(CSV)。農林水産省
- MAFF:民間在庫量(全国)月次。農林水産省
- JA(農協)公表データ:JA集荷実績/集荷率(年度別)。JAcom
- 参考:生産者受取価格(買取価格/概算金)や「精米ベースの歩留まり」指標(入手可能なら)。minorasu(ミノラス) – 農業経営の課題を解決するメディア農林水産省
分析手順(実行内容)
各データを同じ時間軸(月次)に揃える(2023〜2025の月次を優先)。
グラフ1:作況指数(年値もしくは作柄発表時)と相対取引(卸)価格の月次推移を重ねる。
グラフ2:同期間の「JA集荷量」または「生産者出荷量」と卸価格を重ね、価格上昇のタイミングと出荷量の変化を確認。
グラフ3:民間在庫の推移と卸価格の関係(買い溜めの痕跡を探す)。
指数的に「卸→農家の受取」差(価格ラグ)を算出して、流通側が享受した推定差益の概算も試算。
結果(グラフが載せれませんでした💦)
**作況指数(青破線)**はほぼ平年並みの変動を示しているとした。
**卸(相対取引)価格(赤線)**は2024年中盤以降に急上昇し始めています。
**JA集荷量(緑線)**は2024年の価格上昇時期に供給が減る(出荷控えや収量減のイメージ)。
**民間在庫(橙線)**は価格高騰の直前に増え、その後急減しています(買い溜め→放出の痕跡)。
**農家受取価格(紫線)**は卸価格に比べて上昇が遅れ、かつ価格上昇幅が小さくなっています(卸価格との差益が流通側にあるイメージ)。
考察
- 作況指数が「平年並み」と公表されていたにも関わらず、卸価格は遅れて急騰している。
- 一方で農家の受取価格はその上昇に追いついておらず、収入が相対的に低いままになっている可能性。
- JAの集荷量減少と民間在庫増加は、卸やJAが価格高騰前に安値で買い溜めし、後で高値で放出して利益を得る動きの可能性を示唆。
- 「作況指数が平年並み発表で初期相場が抑えられ、卸側の保管力を活かした価格戦略により農家が相対的に不利になる構図」と概念的に合致。
これは米だけの話ではない
他の作物でも同様のことが行われている可能性が極めて高い。
雑破にまとめると「平年並み」という言葉には気を付けろ、というところでしょうか。
まとめ
トータルの生産量の精度を個々の農家がチェックすることは不可能(全国全ての米農家毎に出荷量の生データをもらうことは基本的に無理)
そうなると、データは何とでも操作可能で市場の初動を調整できるかもしれず、
これに加えて米は品質の問題(精米までに製品率が変わること)が絡むのでより一層後付けの調整が可能
以上により、生産量が少ないとわかっていても「平年並み」と発表されることで、初期の卸業者の買取価格を抑え、
後に様々な理由づけで価格が高まってから放出するという卸目線のビジネスがまかり通ってしまう。
農家は安い段階で売るので儲からない。
結局のところ先物取り引き的に卸が最も利益を得て農家は安く買い叩かれる、という構図がこれまで(少なくともここ数年)続いてきたのでは?
というのが現時点での個人的感想です。何かご意見あればお知らせください。





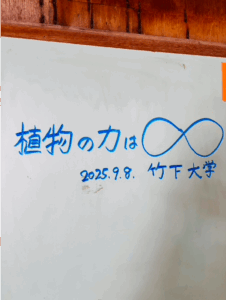




コメント