〜農業の未来を担う国内若手育成の必要性〜
近年、私の周囲でも技能実習生(主にアジアから)受け入れについての議論が活発化している。
当初は難色を示していた人でも、実際の技能実習生と接してみると、そのハングリーさや優秀さ、語学習得の早さに圧倒され、「日本人よりも頼もしい」と感じることも少なくない。
農業現場において、人口減少の中で優秀な人材が地方や過疎地域に来てくれるのは喜ばしいことだ。
しかし、既に高い能力を持つ海外人材を短期契約で受け入れるだけで、次世代の日本農業にとって本当にプラスになるのかという疑問は残る。
エース補強だけでは勝ち続けられない
野球に例えるなら、他チームからエース級を引き抜いて補強するようなものだ。
確かに即戦力にはなるが、自チームから若手が育たなければ、数年ごとに補強を繰り返さなければならない。
技能実習生が長期的に同じ地域に残るケースは稀で、多くは契約満了とともに帰国する。
日本の相対的地位は低下を続け、農業の持続可能性も揺らいでいる。
自分たちで食料を作る能力は今後ますます価値を高めるはずだ。
そのためには、国内の若手が農業技術を学び、継承する仕組み作りが不可欠である。
国内にいる“潜在的な人材”に目を向ける
日本の労働人口は15歳から65歳とされる。
人口減少が進む一方、2025年時点でも15〜22歳の若年層は約1,300万人存在する。
都市部が多くを占めるだろうが、地方でもこの世代の一部を農業に引き込むことは可能だ。
この世代に対して農業スキルを提供し、自国内で作物生産レベルを高めていくことは、未来への教育的投資である。
海外の優秀な人材に比べると未熟かもしれないが、それでも興味ある若者には農業に飛び込み、多様なスキルを身につけてもらいたい。
具体的な仕組み例:「フルーツファンディング」
私たちcog-labでは、高校生や大学生を対象に農業体験を年間通じて提供する「フルーツファンディング」を行っている。
参加者は作物を一過性ではなく通年で育て、栽培の知識・技術・忍耐力を学ぶ。
これが将来「やっていてよかった」と思えるスキルになると確信している。
9月には多くの大学生が来てくれる予定だ。
技能実習生と若手を“ペア”に
海外から優秀な技能実習生が来てくれるのは喜ばしいことだ。
だからこそ、彼らを単なる労働力ではなく「指導者・モデル」として活用し、日本の若者とペアで作業させるべきだ。
これにより、短期的な労働力確保と長期的な国内人材育成を同時に実現できる。
結論
技能実習生の受け入れは、日本農業の現場を支える重要な手段である。
しかし、それだけに頼るのではなく、国内の若手を育てる仕組みを並行して整えることで、未来の農業の土台を築くべきだ。
即戦力と育成力、この両輪を回すことが、日本の農業を持続可能にする鍵である。
個人的に
優秀な海外勢と一緒に仕事ができることは、非常にイイ刺激であり、学ぶことが多い。
田舎に根を張りつつも、世界じゅうの優秀な人々と働けたら嬉しい。





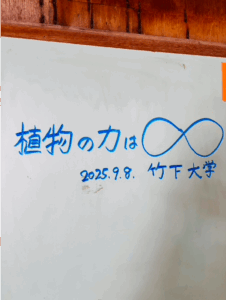




コメント